※2012年12月1日より新ブログに移行しました。
>>>現行ブログ free to write WHATEVER I like
⇒2019年にさらにWordpressに移行しました。
>>>現行HP シャイン経営研究所(中小企業診断士・谷藤友彦)
⇒2021年からInstagramを開始。ほぼ同じ内容を新ブログに掲載しています。
>>>Instagram @tomohikoyato
新ブログ 谷藤友彦ー本と飯と中小企業診断士
April 11, 2012
効率一辺倒ではなく「冗長性」を取り込んだBPR(業務改革)の必要性
拍手してくれたら嬉しいな⇒
以前の記事「BPR(Business Process Re-engineering:業務改革)の火付け役=マイケル・ハマーの誤算」への補足。同記事では、マイケル・ハマーが後年の著書"Beyond Reengineering: How the Process-Centered Organization Is Changing Our Work and Our Lives"(『リエンジニアリングを超えて』)の中で、自身の行き過ぎた手法を反省していることを述べたが、たまたま野中郁次郎教授の同じタイトルの論文を見つけたので読んでみた。
野中氏によると、「官僚制の『逆機能』を排除し、階層・分業・専門化の縦型組織から、境界横断的な横型組織の運営を開発する試み」であるリエンジニアリングは、実は日本的経営と共通点が多いという。
だから、敢えてこういった冗長性を最初から組み込んだ戦略策定プロセスやビジネスプロセスデザイン、組織デザインの方法を考え出す必要があると思う。あくまでもアイデアベースだが、1つには戦略策定の段階で、コアとなるターゲット顧客層に加えて、サブとなる小規模の顧客セグメントをいくつか定め、そのセグメントに対するマーケティングや製品開発・販売などを通じて若手社員や新人マネジャーの育成を狙う、というアプローチがあり得るだろう。
また、ドラッカーはイノベーションを起こすためには「非顧客を観察せよ」と繰り返し説いていることから、例えば営業担当者に本来の担当顧客とは全く異なる属性を持つ顧客をわざと訪問させ、自社の製品を見せたらどういう反応を見せるのか?彼らはどういう潜在ニーズを持っているのか?などを探ってもらうタスクを追加する、というのも1つの手かもしれない。
 | Beyond Reengineering: How the Process-Centered Organization Is Changing Our Work and Our Lives Michael Hammer HarperBusiness 1996-07-04 Amazonで詳しく見るby G-Tools |
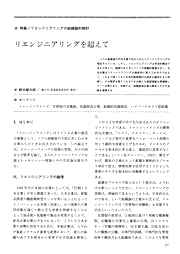 | リエンジニアリングを超えて 野中郁次郎 白桃書房 1994-09-20 booknestで詳しく見るby G-Tools |
野中氏によると、「官僚制の『逆機能』を排除し、階層・分業・専門化の縦型組織から、境界横断的な横型組織の運営を開発する試み」であるリエンジニアリングは、実は日本的経営と共通点が多いという。
日本企業の組織図は表層的には、階層・分業・専門化されていて、それなりの職務分掌規定もあるが、実際には組織性インはそのような原理に則って仕事をしているというよりは、職務の幅を柔軟に変化させながら自在なプロセスで仕事を行なっている。さらに(リエンジニアリングの特徴の1つである)コンカレント・エンジニアリングは、日本企業では、とりわけ新製品開発においてほとんどの企業が行なっているのである。しかし一方で、リエンジニアリングと日本的経営の決定的な違いの1つが「冗長性の有無」である。冗長性とは、異なる成員が似たような仕事をしていたり、当面は必要のない情報を持っていたりすることを意味する。野中氏は、こうした冗長性を許容しないリエンジニアリングの下では、新しい知識の創造を通じたイノベーションが生まれないのではないか?と指摘している。
リエンジニアリングは顧客をリサーチし、他社をベンチマークしながら、最短のプロセスを情報技術を最大限に活用して設計するため、論理的にはきわめて効率的であるといえる。これに対し日本型のビジネス・プロセスは、いかにも冗長性が高い。しかし一方で、市場は分析的に把握できるという前提から、一切の冗長性を切り捨てたリエンジニアリングでは、市場に適応できてもより主体的な市場創造ができるかどうかは疑問である。私もコンサルタントとして多少なりとも戦略策定プロジェクトや業務改革プロジェクトに携わってきたけれども、極限まで合理化された戦略策定プロセスやBPRは、様々な冗長性を排除してしまう。イノベーションに向けた現場レベルでのアイデアの創出や実験、(特に若手社員の)人材育成、戦略の前提となるビジョンや組織文化の共有などは、真っ先に排除されるタスクの代表例である。しかし、中長期的な視点で見ればこういう仕事が重要であることを、多くの人は頭の中で理解しているものである。
だから、敢えてこういった冗長性を最初から組み込んだ戦略策定プロセスやビジネスプロセスデザイン、組織デザインの方法を考え出す必要があると思う。あくまでもアイデアベースだが、1つには戦略策定の段階で、コアとなるターゲット顧客層に加えて、サブとなる小規模の顧客セグメントをいくつか定め、そのセグメントに対するマーケティングや製品開発・販売などを通じて若手社員や新人マネジャーの育成を狙う、というアプローチがあり得るだろう。
また、ドラッカーはイノベーションを起こすためには「非顧客を観察せよ」と繰り返し説いていることから、例えば営業担当者に本来の担当顧客とは全く異なる属性を持つ顧客をわざと訪問させ、自社の製品を見せたらどういう反応を見せるのか?彼らはどういう潜在ニーズを持っているのか?などを探ってもらうタスクを追加する、というのも1つの手かもしれない。
July 18, 2011
今月号はインド企業の事例がいっぱい―『ビジネスモデル 構想と決断(DHBR2011年8月号)』
拍手してくれたら嬉しいな⇒
 |
posted by Amazon360
(レビューの続き)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
企業と社会起業家の有機的パートナーシップ ハイブリッド・バリューチェーン(ビル・ドレイトン、バレリア・バディニッチ)
いまや営利団体は、これらCSO(Civil Society Organization:市民社会組織)と力を合わせることで、どちらも単独では解決できなかった大規模な問題に対処できるようになった。このパートナーシップの力は、参加者たちの強みが相互補完的なところにある。すなわち、企業は、その規模、製造やオペレーション二巻sるう専門知識、資金調達力を、かたや社会起業家とCSOは、コスト・ダウン、影響力の大きいソーシャル・ネットワーク、顧客や地域社会に関する深い識見を提供している。企業が新興国でビジネスを展開する際には、「(潜在)顧客にどうやってアクセスするか?」という壁にぶち当たる。新興国における販売チャネルの構築やマーケティング施策の実行には、現地のCSOやNPOとの連携が有効であることを示している。なお、NPOとの連携については、DHBR2008年1月号にC・K・プラハラードの論文が載っているので、ご参考までに。
 |
posted by Amazon360
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-手つかずの巨大市場を攻めよ 新興国ミドル市場で成功する条件(マシュー・J・アイリング他)
多くの企業は、新興国市場の貧困層にローエンドの製品やサービスを大量に販売することで利益を確保するという誘惑に負けてしまっている。しかし、ハイエンドの製品やサービスは、それに手が届く少数の人々には、新広告市場においても入手可能だ。世界じゅうほとんどどこでも、<メルセデス・ベンツ>や洗濯機を買えるし、高級ホテルに泊まることもできる。「BOPではなく、ミドル市場にアプローチせよ」という論文。ミドル市場はグローバル企業にとって魅力的である反面、現地企業との競争が最も激しい市場でもある。しかし、ミドル市場で成功する秘訣は、それほど特別なものではない。つまり、顧客をじっくりと観察して潜在ニーズを浮き彫りにし、最適な製品やサービスを開発・提供するという、ビジネスのいろはの「い」である。よくある定量的な市場調査に頼るのではなく、文化人類学者のように顧客に密着し、五感を通じて情報を収集することが重要だと著者は言う(いわゆる「エスノグラフィー・マーケティング」である)。
我々の経験から、より将来性のある、参入すべき場所を提供しよう。それは、両極の間にある、巨大なミドル市場である。この層の消費者は、特定の所得層よりも、一般的な暮らしによって定義される。つまり、ミドル市場のニーズは、ローエンド向けソリューションではほとんど満たされていない。なぜなら、ハイエンドの代替品のなかで最も安いものであすら、手が届かないからである。
本論文には、インドのとあるミドル層向けの冷蔵庫の事例が登場する。この層は、月収が5,000〜8,000ルピー(約125〜200ドル)程度であり、一部屋に家族4、5人と暮らし、頻繁に引越しをするという特徴がある。彼らは、従来型冷蔵庫を自家用に所有する余裕がないため、共用の中古冷蔵庫を利用していた。
彼らは、富裕層向けの冷蔵庫(=先進国で使われているような冷蔵庫)ほどの機能を必要としない。頻繁に食料品を購入し、引越しを繰り返す彼らにとって必要なのは、2、3日程度の食料が保存でき、かつ持ち運びが便利な小型の冷蔵庫であったという。
エスノグラフィー・マーケティングに関連する記事は、過去にもいくつか書いたことがあるので、リンクを掲載しておきます。
「顧客のことは顧客でも解らないことがある−『マーケティングこそすべて(DHBR2010年10月号)』」
「P&Gが顧客(=ボス)との距離を極限まで縮めるためにやっていること―『ゲームの変革者』」
個人的には、エスノグラフィー・マーケティングなどという難しい言い方をしなくても、顧客をじっくりと観察して真のニーズを発見するというのは、ビジネスの基本中の基本だと思う。しかしながら、こうした取り組みに本腰を入れている企業がどの程度あるのかはやや疑問である。
一般的な市場調査を行えば、必ずレポートという形で成果物が残る。また、1回の調査で数多くの顧客の情報を収集することができるし、統計的な手法を用いて様々な示唆を導くことも可能である。だから、市場調査を行えば、何かしら仕事をした気分になってしまうのだ。
仮に、大した分析結果が得られなかったとしても、「今回の調査対象者は、わが社のターゲット顧客にはならないのだろう」といった感じで片づけられてしまう。「戦略とは、”何をやらないか”を決めることでもある」というM・ポーターの有名な言葉に従えば、「特定の層が自社のターゲットに該当しない」ということも、重要な発見として重宝されるのである。
一方、エスノグラフィー・マーケティングは時間も手間もかかるし、調査担当者の主観が入りやすい。それに加えて、必ず成果物が残るとは限らない。場合によっては、めぼしい発見が何も得られないことだってありうる。しかし、市場調査とは異なり、エスノグラフィー・マーケティングの場合は、何も発見がなければ、「君たちは会社の金を使って、ただブラブラしていただけではないのか?」という疑惑の目を向けられてしまう。
エスノグラフィー・マーケティングのリスクやコストを承知の上で、こうした取り組みに寛容な姿勢を見せる企業だけが、新興国のミドル市場で現地企業とまともに勝負する資格を獲得するのだろう。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
すべてのステークホルダーの経験価値を共有する 人間中心の共創型事業をつくる(ベンカト・ラマスワミ、フランシス・グイヤール)
エンド・ユーザーのために新しい経験を生み出すには、内部関係者にとっての経験を改善しなければならない。これは従来のプロセス分析でしばしば見逃されてきた事実である。全てのステークホルダーと言っても、実際には社員と取引先に焦点が当たっており、株主や債権者、社会的利益の保護を求めるNPOや消費者団体は本論文のスコープ外なので要注意。本論文で分析されているのは、「ES(社員満足度)向上⇒「CS(顧客満足度)向上」⇒「業績向上」という流れである。ちなみに、このチェーンについても、過去に記事をアップしたことがあるので、ご参考までに。
「「ES向上⇒CS向上⇒利益向上」の自己強化システムについての考察−『バリュー・プロフィット・チェーン』」
「「ES向上⇒CS向上のサイクル」をサプライチェーン全体に広げてみたら―『バリュー・プロフィット・チェーン』」
通常のBPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)では、ターゲット顧客と顧客価値を定義した上で、その価値を最も効率的・効果的に提供できるプロセスを描き、そのプロセスを支えるIT基盤や組織構造、予算配分のルール、適材適所を実現する人事システムといった様々な仕組みをデザインしていく。著者は、このような従来型の方法では、顧客満足度だけが過度に偏重されており、社員や取引先、協力企業の利害が考慮されていないと指摘している。この点は確かに「なるほど」と思った。
本論文では、社員満足度の向上の視点から金融商品の販売プロセスをデザインしたヨーロッパの大手銀行や、サプライヤの満足度向上の視点から農作物の生産・流通プロセスを刷新したインド企業の事例が紹介されている。
インドのコングロマリット企業であるITCは、インド農家の農作物が国際市場で求められる水準に達しておらず、農家の生産性が低すぎることに頭を抱えていた。従来型のBPRアプローチならば、ITCは農地を集約して大規模農家にし、品質の改善など厳しい条件をつけた売買契約を取りつけたことだろう。
しかしITCは、低い生産性と少ない収入に苦悩する小規模農家の思いと、独立したままでいたいという彼らの切なる願いに共感し、貧困からの脱出を手がけるというアプローチをとった。具体的には、ITを活用した農業技術・ノウハウの提供や、伝統的な国営市場(この市場は腐敗しており、重量や価格のごまかしや支払い遅延に農家が悩まされていた)とは違う、透明で公正な取引を実現する市場の設置などを行った。その結果、農作物の品質と生産性は向上し、ITCは満足のいく農作物が入手できるようになったのとともに、農家にも収入増がもたらされたという。
先ほどの「「ES向上⇒CS向上のサイクル」をサプライチェーン全体に広げてみたら―『バリュー・プロフィット・チェーン』」では、P&Gとウォルマートの事例に言及し、「P&Gの社員満足度の向上がウォルマートの仕入担当者の満足度にどのように影響し、ウォルマート全体の社員満足度にどう作用するか?」についての分析があると、もっと面白かっただろう、といった趣旨の内容を書いた。前述のITCの事例を読むと、サプライヤ(=農家)の満足度の向上が、顧客(=ITC)の満足度の向上につながっていることが(定性的ではあるが)うかがえる。
June 29, 2011
「業務プロセスがイノベーションの原動力」というのは別の意味で一理あり―『イノベーションの新時代』
拍手してくれたら嬉しいな⇒
 | M・S・クリシュナン、C・K・プラハラード 日本経済新聞出版社 2009-06-11 おすすめ平均:   「個客経験の共創」と「グローバル資源の利用」の価値創造戦略 「個客経験の共創」と「グローバル資源の利用」の価値創造戦略 主張に新規性なし 主張に新規性なし 肩すかし 肩すかし |
posted by Amazon360
1ヶ月ほど前に紹介した本をまた取り出して記事を書いてみる(しつこい(笑))。本書はゲイリー・ハメルとの共著『コア・コンピタンス経営』で知られるC・K・プラハラードの著書であるが、本書のポイントは「イノベーションの源泉が”業務プロセス”にある」という点である。
通例には反するが、本書では、戦略、業務、ビジネスモデルなどを切り口としたイノベーションの分類は重視しない。ここでもまた、イノベーションの基本原則−個客経験の協創とグローバル資源の利用−をめぐる議論と同じく、イノベーションのおもな原動力に注目したい。業務プロセスは、組織にとっていわば血流のようなものである。イノベーションにはさまざまな形があるが、たとえ形は違ったとしても、イノベーションを生み出す気風は共通の土台に支えられている。それが、融通の利く、磨き上げられた業務プロセスである。ただ、本書を読む限り、「業務プロセスはイノベーションを着実に実行するために必要である」、言い換えれば、「新しい戦略が画餅に終わらないようにするために、新しい戦略に適合した業務プロセスを構築しなければならない」という、至極当たり前のことを言っているだけのように感じる。
しかし、私が思うに、業務プロセスがイノベーションの源泉になるというのは、別の意味で真実である。なぜなら、イノベーションは「例外」から生まれることが多いからだ。そして、例外を判断する基準となるのが、標準的な業務プロセスなのである。
ここでいう業務プロセスとは、製品やサービスを製造・販売するプロセスに加えて、その製品やサービスが提供している経験価値や、その経験価値を享受するターゲット顧客、さらにはプロセスを支える組織構造やITインフラ、社員の人数やスキル、人事異動のルールや評価制度、予算管理の仕組み、ナレッジやノウハウ、意思決定の構造、その他諸々の社内ルールまでを含めた、統合されたシステムであると捉えていただきたい。
マネジメントの定石としては、まずはターゲット顧客とその顧客に提供したい価値を定義し、その価値が具現化された製品やサービスを企画する。次に、その製品やサービスを最も効果的、効率的に生産・販売できるプロセスを構築する。そして、プロセスが円滑に運用されるよう、ヒト、モノ、カネ、情報、知識といった経営資源を、どのプロセスにどの程度投入するかをルール化していく。こうしたルールが、組織構造や予算配分の方法、人事制度などといった社内の様々な仕組みに反映されていく。これらの多様な要素が一貫した形でがっちりと組み合っていれば、企業は高い競争力を手に入れることができる。
だが、この統合されたシステムに矛盾をきたすような「例外」が、日常業務の中ではしばしば起こる。例えば、「想定外の顧客に製品がよく売れる」とか、「全く眼中になかった販売チャネルから、わが社の製品を扱いたいとの依頼が来る」といった具合である。こうした例外こそが、イノベーションの源泉になると思うのである。
ドラッカーはイノベーションの「7つの機会」を整理しているが、最も頻度が高く、かつ最も成功の可能性が大きい機会として「予期せぬ成功」を挙げている。実際に、「予期せぬ成功」がイノベーションにつながった事例が、ドラッカーの著書『イノベーションと起業家精神』の中でいくつか紹介されている。その中から1つだけ引用しておこう。
 |
posted by Amazon360
動物用医薬品業界において、世界の主導的な地位を占めているスイスの医薬品メーカーがある。しかし、扱っている動物用医薬品のうち、自ら開発したものは1つもない。それらの医薬品を開発したメーカーが、動物用医薬品市場に進出することを嫌ってくれたために扱えるようになったにすぎない。開発メーカーの業務プロセスは、人間用医薬品の開発・製造・販売に適したものになっていたことだろう。仮に獣医に向けて販売することになれば、調合や包装のプロセスも変えなければならないし、マーケティングも人間用医薬品と動物用医薬品の両方について実施する必要が出てくる。さらに販売チャネルについても、人間用と動物用が入り混じった複雑なものになるだろうし、自社の営業担当者には、獣医用医薬品の知識を新たに叩き込まなければならない。
抗生物質を中心とするそれらの医薬品は、もともと人間用に開発したものだった。したがって、獣医たちが注文を寄こしたとき、開発したメーカーは喜びはしなかったし、ときには売ることさえ拒否した。当然、動物用に調合を変えたり、包装を変えるようなことはしなかった。(中略)
人間用の医薬品は、世界中で激しい価格競争にさらされ、しかも行政による厳しい規制を受けるようになった。その結果、今日では、動物用医薬品が医薬品業界で最も利益率のよい分野になった。だが、その利益を享受しているのは、それらの医薬品を開発したメーカーではない。
開発メーカーは、長年にわたって統合的なシステムを構築してきた。それを変更する作業があまりにも厄介に感じられたため、動物用医薬品という新しい市場の魅力が見えなくなってしまったのであろう。だから、獣医からの注文という例外に出くわしても、それをイノベーションの機会ではなく、単なる厄介な問題として片付けてしまったと推測される。逆に、例外をイノベーションの機会と捉えたのが、スイスの医薬品メーカーであったわけだ。
「例外」は、毎日いろんな顧客に接し、細かいプロセスをいくつも遂行している現場の人間の方が気づきやすいかもしれない。こうした例外から新しいビジネスを作り出していく人材が現場付近に溢れている企業こそが、イノベーションに強い企業となるであろう。NRIラーニングネットワークの亀井敏郎氏は、こうした人材を一般的な経営職(CXO)や管理職と区別して「経営職ミドル」と呼び、その役割を次のように説明している。
 |
posted by Amazon360
(経営職ミドルは、)顧客の立場で問題を発見し、収益が上がる形でその解決策を提供しなくてはならない。これはビジネスプロセスの設計の問題であり、収益性の観点から業務の流れをつくりあげることだ。それには自社の強みや弱み、経営資源の特性などが関連してくるため、自社のことをよく知らなければできないのである。
顧客と自社の間に新しい業務の流れをつくり出す一方で、顧客接点となる現場では、組織としてのマネジメントも求められる。顧客の立場を重視した業務を円滑に進めていくためには、担当するメンバーの配置や指揮・命令系統の整備、さらには個々のモチベーションの維持・向上が必要になるからだ。これは経営のミニチュア版であり、「現場の会社化」という考え方である。経営職ミドルは、自社が本来想定してた顧客ニーズと、それに合致すると思って用意した製品・サービスが、目の前にいる顧客にはうまくマッチしない場合でも、社内の資源(時には社外の資源も)をうまく組み合わせて最適なソリューションを提供する。この場合、往々にして標準的な業務プロセスとは違ったプロセスが構築される。経営職ミドルの1つ1つの解決策だけを見ればさほどインパクトはないかもしれない。ところが、複数の経営職ミドルが似たような新しいソリューションを提供するようになれば、それはイノベーションへとつながっていくだろう。
経営職ミドルがイノベーションを創出できるのは、突出した才能のおかげとは限らない。自社が用意した標準プロセスがあるからこそ、経営職ミドルは「例外」を発見できると考えられる。この意味で、業務プロセスはイノベーションの源泉と言えるのである。
多くの企業は標準プロセスを用意した上で、プロセスの成果を図るための指標を設定し、目標値を定めている。そして、いわゆる「進捗会議」を開いて各指標の値をモニタリングし、目標に届かなかった場合は、その原因を分析する。ところが、標準プロセスに該当しない「例外」を会議の材料にして、
「その例外は自社にとって何を意味するのか?」
「本当に単なる例外として片付けていいのか?」
「実は、自社が見過ごしていた新しいビジネスチャンスがあるのではないか?」
「その例外に目をつけている他の企業はいないのか?」
「いるとすれば、その企業はどのような対応策をとっているだろうか?」
などといった論点について対話を繰り広げている企業はまだまだ少ないのではないだろうか?(このような対話の場については、「進捗会議」のような適切な語句が見当たらないことからも解る)逆に、そういう対話ができる企業は、イノベーションの機会を他社よりも上手に発見するに違いない。


