※2012年12月1日より新ブログに移行しました。
>>>現行ブログ free to write WHATEVER I like
⇒2019年にさらにWordpressに移行しました。
>>>現行HP シャイン経営研究所(中小企業診断士・谷藤友彦)
⇒2021年からInstagramを開始。ほぼ同じ内容を新ブログに掲載しています。
>>>Instagram @tomohikoyato
新ブログ 谷藤友彦ー本と飯と中小企業診断士
April 17, 2012
反証をぶつけて科学的研究の厳密さに迫るHBRのインタビュアーが秀逸―『幸福の戦略(DHBR2012年5月号)』
拍手してくれたら嬉しいな⇒
![Harvard Business Review (ハーバード・ビジネス・レビュー) 2012年 05月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51R3p4KlCqL._SL160_.jpg) | Harvard Business Review (ハーバード・ビジネス・レビュー) 2012年 05月号 [雑誌] ダイヤモンド社 2012-04-10 Amazonで詳しく見るby G-Tools |
些細な出来事の積み重ねが幸福感を左右する 幸福の心理学(ダニエル・ギルバート)
毎日、些細なことが十数回起こる人は、本当に驚くほど素晴らしいことが1回だけ起こる人よりも幸せである可能性が高いのです。ですから、楽な靴に履き替えたり、奥さんに派手なキスをしたり、フライドポテトを1本こっそりつまみ食いしたりしてみてください。些細なことのように聞こえますし、実際に些細なことです。しかし、その些細なことが大事なのです。ハーバード大学心理学部のダニエル・ギルバート教授に対するHBR誌のエディターのインタビュー記事。「些細な出来事の積み重ねが幸福感を左右する」という点は、先日紹介した論文「幸せな気持ちになると、何事もうまくいく PQ:ポジティブ思考の知能指数」(ショーン・エイカー)と共通である。それよりもこの記事は、インタビュアーの質問の切り口が素晴らしいと感じた。そのいくつかを紹介したいと思う。
(中略)我々は、1つか2つの大きな出来事が深い影響を与えると想像しがちですが、幸福は無数の小さな出来事の総和のようなのです。
―その(幸福という)尺度自体が主観的なのではありませんか。あなたにとっての5点が、私には6点ということもありうるのではないでしょうか。
この問いに対してギルバート教授は、例えば100人のうち半数の人をインフルエンザウイルスに感染させ、正確な体温を測定できない粗悪な体温計で体温を測らせると、ウイルスに感染した人々の平均体温は、ほぼ確実にそれ以外の人々の平均体温よりも高くなると答えた上で、次のように述べている。
実際よりも高い温度や低い温度を表示する体温計であったとしても、十分な人数を測ることによって、不正確さは相殺されます。測定器具の精度が低くても、多くのグループを測定すれば、比較は可能なのです。インタビュアーの質問の意図もよく解るし、教授の例も解りやすいと思った。ただ、だからと言って、例えば各国の幸福度を比較する際に、単に「あなたは幸福ですか?」という質問だけを投げかけて、その平均スコアを国別に比較すればよいかというと、そういうわけにもいかないだろう。というのも、幸福の意味は多義的であるし、国や地域、文化、民族などによって何にウェイトを置いているかが異なるからである。
だから、実際の研究では、幸福を構成する要素(例えば仕事、収入、家庭環境、コミュニティ、地域行政、教育・医療サービス水準など)を特定し、それぞれの要素を人生においてどの程度重視しているのか?そして、各要素について現在どの程度幸福感を抱いているのか?を尋ねることになるはずである。これはちょうど、社員満足度調査で、社員満足度を構成する要素を分解し(例えば仕事の難易度、理念やビジョンへの共感度合い、上司・同僚との関係、評価への納得感、給与水準、職場へのアクセス、福利厚生など)、それぞれの重要度と満足度を質問するのと同じである。
―ベートーベンやゴッホ、ヘミングウェイなどの不幸な天才芸術家のことを考えると、ある程度の不幸が刺激となって優れた業績が導かれたのではないでしょうか。
ある論点を明らかにする際に、逸話を用いる場合と、科学を用いる場合の違いを考えるなら、後者の場合、都合のよい話を選ぶだけでは済まされないことです。事例をすべて検討するか、少なくとも、そこから妥当な標本を抽出して、「不幸ながらも独創的な人は、幸福で独創的な人よりも多いか」「悲惨で独創的でない人は、幸福で独創的でない人よりも多いか」を確認しなければなりません。例外的な事例をめぐる問答。確かに、統計的な処理をして「例外は例外」と片付けてしまうのは一理あるし、その方が簡単ではある。しかし、個人的には例外には着目すべき価値があると思っている。なぜならば、例外は「ブラック・スワン」であるかもしれず、新しい法則をもたらす可能性を秘めているからだ(以前の記事「人間の理性の限界を徹底的に茶化してるな−『ブラック・スワン』」を参照)。
もし不幸が独創性を促すとすれば、幸せな人々よりも、悲惨な状況にある人々の間で、独創的な人の比率が高くなるでしょう。しかし現実にはそうはなりません。概して、幸福な人のほうがより独創的で生産的なのです。
―多くのマネジャーは、充足している社員はあまり生産的ではないので、自分の仕事に少し居心地の悪さ、おそらくは多少の不安感を与え続けたほうがよいと言うでしょう。
直感に頼るスタイルのマネジャーではなく、データを集めるマネジャーならば、そうは言わないでしょう。私が知る限り、気をもみ、おびえている社員のほうが独創的かつ生産的であることを示すデータはありません。(中略)適度に挑戦しがいがある時、すなわち困難ではあるが、手が届かなくもない目標を達成しようとしている時に、人は最も幸福であることがわかっています。昨日の記事「「幸福感」と「モチベーション」の違いがよく解らない印象を受けた―『幸福の戦略(DHBR2012年5月号)』」のように、幸福感とモチベーションを区別して考える立場からすると、インタビュアーがこの質問をした気持ちは非常によく解る。ただ、回答では幸福感とモチベーションが区別されていないようなので、どこか引っかかる感じが否めない。
「困難ではあるが、手が届かなくもない目標」が、「モチベーション」を高めるという研究があるのは知っている。例えば、「目標設定理論」がそうであるし、ジェームズ・コリンズも、ビジョナリー・カンパニーは「BHAG(Big Hairy Audacious Goal:大胆で野心的な目標)」によって社員を動機づけると指摘している。だが、それが果たして同時に幸福感にもつながるのかどうかは、個人的にはあまりよく解らないところだ。
April 16, 2012
「幸福感」と「モチベーション」の違いがよく解らない印象を受けた―『幸福の戦略(DHBR2012年5月号)』
拍手してくれたら嬉しいな⇒
![Harvard Business Review (ハーバード・ビジネス・レビュー) 2012年 05月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51R3p4KlCqL._SL160_.jpg) | Harvard Business Review (ハーバード・ビジネス・レビュー) 2012年 05月号 [雑誌] ダイヤモンド社 2012-04-10 Amazonで詳しく見るby G-Tools |
DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー2012年5月号の書評。定期購読を始めてかれこれ7年近くになるのだが、「幸福」をテーマにした特集は初めてじゃないかな??
社員のパフォーマンスを高める 幸福のマネジメント(グレッチェン・スプレイツァー、クリスティーン・ポラス)
我々が安定的に高業績を上げている組織の秘訣について調査したところ、「幸福感を抱く社員は、そうでない人と比べて長期にわたって高いパフォーマンスを上げる」ということが明らかとなった。欠勤が少なく、離職率が低く、求められた以上の働きをし、自分たちと同様に意欲の高い人材を引き寄せるのだ。しかも、短距離走よりもマラソン向きだといえ、すぐに息切れするようなことがない。この論文に限らず、今月号の特集に共通して言えることだけれども、「幸福感」と「モチベーション」、さらには「社員満足度」との違いがいまいちよく解らなかった。引用文の「幸福感を抱く社員」の部分を、「モチベーションが高い社員」とか、「社員満足度が高い社員」に置き換えても文章として十分成立するし、実際そのような結果を示す研究もある。
社員の幸福感をマネジメントの新しい課題に据えるのであれば、類似概念であるモチベーションや社員満足度との関係をもう少し厳密に整理する必要があると思う。少なくとも幸福感、社員満足度とモチベーションの間には大きな違いがある。それは、幸福感や社員満足度がもっぱら「現在から過去を振り返ってどう感じるか?」を測定している点で”過去志向”であるのに対し、モチベーションは「次の仕事に対するやる気があるか否か?」を問うている点で”未来志向”であるということである。
したがって、幸福や満足は感じていないけれどもモチベーションは高いケース(例:職場での現在の処遇は不満だが、もっといい待遇が受けられるように、今の仕事で高い成果を上げて上司に認めてもらおうとする)もあるし、逆に現状で十分な幸福や満足を覚えてしまったがためにモチベーションが湧かないというケース(例:何年にも渡る困難なプロジェクトをやり切った充足感で今は一杯だから、しばらくは楽な仕事を続けたい)も考え得る。
とはいえ、3つの概念には重なる部分があり、「今日も幸福で満足な一日だったから、明日からまた頑張ろうという気持ちになる」ことも事実である。よって、3つの概念の関係を整理した上で、幸福感や満足感とモチベーションを連続させるにはどうすればよいのか?逆に、どういう状況で人は、幸福感や満足感とモチベーションの連続性が切れてしまうのか?を問うことが重要になるように思える。
幸福感と社員満足度も、似ているようで微妙に異なる概念である。社員満足度は職場に限定されている一方で、幸福感は人生そのものに対する包括的な満足度を指している。だから、厳密にタイプ分けをすれば、幸福ではあるが社員満足度は低い社員(例:もともとプライベート重視志向が強く、現在の私生活は充実している反面、職場には不満がある社員)や、幸福感は低いが社員満足度は高い社員(例:プライベートで問題を抱えており、その問題から逃れるように仕事に没頭する社員)にグルーピングされる人も出てくるはずだ。
一般的に、「幸福感が高い社員はパフォーマンスが高い」、「社員満足度が高い社員はパフォーマンスが高い」とされるが、こういういわば”ねじれた”幸福感や満足感を抱えている社員のパフォーマンスは、果たしてどういうものになるのだろうか?そして結局のところ、企業は幸福感と社員満足度のどちらを重視すればよいのだろうか?(仮に幸福感の方を重視すべきだという見解に立つならば、企業は社員のプライベートにも一定の責任を有することになるわけだが、それは果たして妥当かつ可能なのであろうか?)
放っておいても順調に歩み続ける人材ばかりなら、どれほどよいだろう。しかし、仕事への熱意を引き出し続ける方法はいくつもある。我々の調査からは、そのための環境づくりには、(1)判断の裁量を与える、(2)(業績や重要な意思決定に関する)情報を共有する、(3)ぞんざいな扱いを極力なくす、(4)成果についてフィードバックを行う、という4つの方法が有効であることが明らかになった。この論文では、社員の幸福度を高めるための4つの方法が提案されている。ただ、引用文に「仕事への『熱意』を引き出し続ける方法」とあるように、これらの方法は幸福感を高める方法というよりも、モチベーションを高める方法のような気がする。以前の記事「《メモ書き》モチベーションと業績の関係モデル―『熱狂する社員』より」で、モチベーションを規定する要素は公平感、達成感、連帯感の3つであると書いた。これに従うと、引用文の(1)は達成感、(2)(4)は公平感、(3)は連帯感と公平感につながると考えられる。もちろん、幸福感を高める方法と、モチベーションを高める方法には共通項も多いだろう。しかし、この論文を読む限り、幸福感とモチベーションがごちゃ混ぜにされてしまっている印象が否めない。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
幸せな気持ちになると、何事もうまくいく PQ:ポジティブ思考の知能指数(ショーン・エイカー)
パフォーマンスを向上させる要因として誤解されている最たるものが、おそらく「幸福」であろう。その誤解の1つは、ほとんどの人が「成功すると幸福になれる」と信じていることである。たとえば「昇進すれば、幸福な気持ちになる」とか、「営業目標を達成できれば最高である」と考える。論文の著者によれば、「幸福優位」とは「幸福を感じていると成功確率が高まる」ことである。しかも、幸福を感じるのに大げさな出来事は必要ではなく、「1日1回前向きな行動を3週間続けると、その影響がずっと続く」のだという。ここで問題になるのはやはり、幸福優位の原則に従っている社員の高い幸福感をモチベーションに転換するためには、企業はどうすればよいのか?反対に、企業はどのようなことをすると、幸福優位の原則に従っている社員のモチベーションをくじいてしまうのか?(=つまり、成功確率を下げてしまうのか?)ということではないだろうか?
しかし、成功はたえず変化していく。ある目標を達成したとたん、さらに高い目標が生まれる。成功によって生まれる幸福感はうたかたにすぎない。実際には、「まず成功ありき」ではない。ポジティブ思考を養ってきた人は、困難に直面したときこそ、通常以上の結果を出す。これを、私は「幸福優位」(happiness advantage)と呼んでいるが、脳が活性化している時には、ビジネス関連の成果がもれなく改善されることが示されている。
《2012年7月15日追記》
”過去志向”の社員満足度と”未来志向”のモチベーションを区別することが重要ではないか?という話は、「顧客満足度」にも当てはまる。社員満足度は高いがモチベーションは高くない社員がいるのと同様、顧客満足度は高いが「再購買意向」は高くない顧客がいる可能性がある。言い換えれば、顧客はある企業の製品やサービスに”今回は”満足したけれども、”次回も”同じ企業から購入するとは限らないのである。
そして、実際にそのような顧客層の存在を裏づけるデータがある。「『顧客満足度』再考〜『顧客満足度』は業績と連動するか〜」によると、業界によっては顧客満足度が高くても、他社にスイッチする顧客が多い。自動車や生命保険、テレビのように、買い替えサイクルが長く、同じ企業の製品・サービスを継続するメリットが少ない業界では、こうした傾向が見られるという。したがって、企業が継続的に収益を上げようとするならば、単に「顧客満足度を高めるにはどうすればよいか?」と問うのではなく、「顧客に『次もわが社から買いたい』と思ってもらうためにはどうすればよいか?」と問う必要がある。
”過去志向”の社員満足度と”未来志向”のモチベーションを区別することが重要ではないか?という話は、「顧客満足度」にも当てはまる。社員満足度は高いがモチベーションは高くない社員がいるのと同様、顧客満足度は高いが「再購買意向」は高くない顧客がいる可能性がある。言い換えれば、顧客はある企業の製品やサービスに”今回は”満足したけれども、”次回も”同じ企業から購入するとは限らないのである。
そして、実際にそのような顧客層の存在を裏づけるデータがある。「『顧客満足度』再考〜『顧客満足度』は業績と連動するか〜」によると、業界によっては顧客満足度が高くても、他社にスイッチする顧客が多い。自動車や生命保険、テレビのように、買い替えサイクルが長く、同じ企業の製品・サービスを継続するメリットが少ない業界では、こうした傾向が見られるという。したがって、企業が継続的に収益を上げようとするならば、単に「顧客満足度を高めるにはどうすればよいか?」と問うのではなく、「顧客に『次もわが社から買いたい』と思ってもらうためにはどうすればよいか?」と問う必要がある。
February 29, 2012
《メモ書き》モチベーションと業績の関係モデル―『熱狂する社員』より
拍手してくれたら嬉しいな⇒
先日の記事「自分自身は信頼するが、未来への希望は下がり始めるミドル層―『ミドルの自己信頼が会社を救う(Works No.110)』」で、リクルートワークス研究所が新たに提唱している「自己信頼」という概念にいろいろと突っ込みを入れたわけだが、同号でも書かれているように、そもそも「自己信頼」と個人や企業の業績との関係はまだ検証されていないとのことである。
ところで、同号を読みながら、根本的な疑問として、「モチベーション」と「業績」はどのように関係しているんだっけ?と思い、本棚から『熱狂する社員』(デビッド・シロタ他著)を引っ張り出してきた。
本書は、社員のモチベーションと業績に関する30年以上の実証研究に基づくものである。1994年以降だけで、89か国、237社におよぶ民間企業、公的機関、非営利団体に勤める250万人ものデータを収集したとのことである。これらのデータを分析した結果、社員の「正のモチベーション」(※「仕事をやりたくない」という「負のモチベーション」もあるので、敢えてこの表現にした。なお、正のモチベーションが強い社員を、本書では「情熱的」と呼ぶ)と企業の業績には強い相関関係が見られるという。
ただ、あくまでも”相関関係”であって、モチベーションと業績をめぐる関係はもう少し複雑である。著者は、モチベーションと業績に影響を与える、あるいはモチベーションと業績から影響を受ける他の因子との関係をまとめて、以下の「人材パフォーマンス・モデル」を提示している。
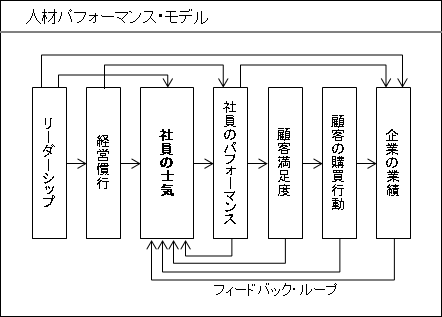
(※本書より筆者作成)
「社員の士気」が高まると、「社員のパフォーマンス」が向上⇒「顧客満足度」が向上⇒「顧客の購買行動」が向上⇒「企業の業績」が向上、という流れで業績向上につながる。さらに、「社員のパフォーマンス」、「顧客満足度」、「顧客の購買行動」、「企業の業績」は、いずれも「社員の士気」に対してブーメランのように跳ね返ってくる因子でもあり、これがフィードバック・ループと呼ばれる。
また、「社員の士気」には、「リーダーシップ」や「経営慣行」が影響を与える。ここで、「リーダーシップ」と「経営慣行」については、それぞれ次のように述べられている。
本書が面白いのは、
ここで、「モチベーション」と「自己信頼」の構成要素を比較してみると、「連帯感」と「良好な人間関係」はぴったり重なると思う。「達成感」には、「過去の仕事の達成感」に加えて、「将来的に大きな仕事をやらせてもらえるかもしれない」という期待も含まれているので、この点では「未来への希望」と重なる部分がある(なお、先日の記事で述べたように、「未来への希望」と「自己への信頼」は部分的に重複している印象があるので、「達成感」と「自己への信頼」も重なる部分があると言えそうだ)。だが、「公平感」に関しては「自己信頼」と重なる要素がない。したがって、「自己信頼」と業績の間に相関関係が見られるかどうかは、個人的にはやや怪しいと推測している。
この量的指標の扱いが、自己信頼の今後の課題でもあるという。たとえば、自己信頼の高い従業員は、上司による評価も高いのか、業績上の成果も上げているのかといった、自己評価ではない客観的指標との相関は、まだ検証されていない。ちなみに、同号で「自己信頼」と類似の概念として取り上げられている「自尊感情(自尊心)」に関しては、定量的に測定する方法が確立されているという。そして、個人の「自尊感情」が高すぎるのも組織にとっては問題であることが明らかになっているそうだ(うぬぼれが強い人は周囲から煙たがられるために、円滑な人間関係を構築できず組織全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼすことは、感覚的にも理解できるところである)。
ところで、同号を読みながら、根本的な疑問として、「モチベーション」と「業績」はどのように関係しているんだっけ?と思い、本棚から『熱狂する社員』(デビッド・シロタ他著)を引っ張り出してきた。
 | 熱狂する社員 企業競争力を決定するモチベーションの3要素 (ウォートン経営戦略シリーズ) デビッド・シロタ スカイライトコンサルティング 英治出版 2006-02-02 Amazonで詳しく見るby G-Tools |
本書は、社員のモチベーションと業績に関する30年以上の実証研究に基づくものである。1994年以降だけで、89か国、237社におよぶ民間企業、公的機関、非営利団体に勤める250万人ものデータを収集したとのことである。これらのデータを分析した結果、社員の「正のモチベーション」(※「仕事をやりたくない」という「負のモチベーション」もあるので、敢えてこの表現にした。なお、正のモチベーションが強い社員を、本書では「情熱的」と呼ぶ)と企業の業績には強い相関関係が見られるという。
ただ、あくまでも”相関関係”であって、モチベーションと業績をめぐる関係はもう少し複雑である。著者は、モチベーションと業績に影響を与える、あるいはモチベーションと業績から影響を受ける他の因子との関係をまとめて、以下の「人材パフォーマンス・モデル」を提示している。
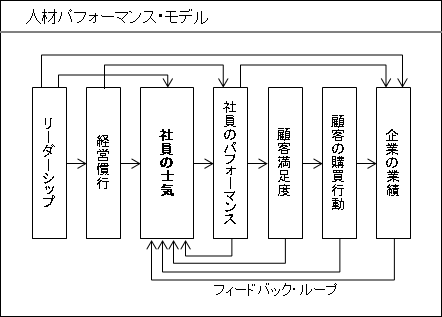
(※本書より筆者作成)
「社員の士気」が高まると、「社員のパフォーマンス」が向上⇒「顧客満足度」が向上⇒「顧客の購買行動」が向上⇒「企業の業績」が向上、という流れで業績向上につながる。さらに、「社員のパフォーマンス」、「顧客満足度」、「顧客の購買行動」、「企業の業績」は、いずれも「社員の士気」に対してブーメランのように跳ね返ってくる因子でもあり、これがフィードバック・ループと呼ばれる。
また、「社員の士気」には、「リーダーシップ」や「経営慣行」が影響を与える。ここで、「リーダーシップ」と「経営慣行」については、それぞれ次のように述べられている。
本書では基本的に、経営者や管理職による日々の経営慣行が、社員の士気にどんな影響を与えるか、それは企業の業績にどうつながるかについて論証している。しかし経営慣行は、社員のパフォーマンスに直接的にも作用する。チームワークを重んじる企業が高業績を上げるのは、仕事のほとんどが共同作業によってパフォーマンスを押し上げられるからであり、またチームワークにより連帯感が満たされ、社員のモチベーションや情熱といった「スピリット」が高まるからだ。(中略)このモデルにおいて、経営慣行は最も重要であり、社員の士気とパフォーマンスに大きく作用する。
日々の経営慣行と同様、経営陣のリーダーシップも社員のパフォーマンスへ直接・間接の影響を与える。経営陣は、事業戦略を決定する。(中略)経営陣、特にCEOの能力と事業戦略の堅実性は、成功のための大きな要素である。事業戦略の堅実性は、ビジネスの成功を社員の士気とパフォーマンスにフィードバックすることで、企業の業績をさらに増幅させるのである。換言すると、「リーダーシップ」とは戦略(引用文では事業戦略に限定されているものの、事業をまたぐ全社戦略も含んでよいと考える)や、企業文化の根幹をなす価値観・行動規範のことであり、「経営慣行」とは社員の職務デザイン、職場での人的ネットワークの形成、業務のモニタリングと支援、育成・教育機会の提供と評価などといった、社員との日常的な接点において生じる様々な具体的言動、ということになるだろうか?
リーダーシップの威力は、企業文化を決定づけることでさらに拡大される。社員重視の度合いが管理職によって異なることはありえるが、たいてい経営陣の傾向と一致している。経営陣が社員を軽んじる企業では、社員を軽視する管理職の割合は跳ね上がる。
本書が面白いのは、
社員から見て唯一最大のモチベーションが何かを突き止めようとするのは時間の無駄である。社員の「最大の」欲求は1つではないからだ。「とにかくお金」や「そのためならすべてを犠牲にできる」のように1つのものだけを追い求めるのは、心理学的には病気である。と前置きをした上で、
人が仕事をするうえでの3つのゴールを、我々はここに宣言する。それは、公平感、達成感、連帯感だ。これを仕事のモチベーションにおける3要素理論として提唱する。と断言している点である(※いずれも太字は原文ママ)。要するに、モチベーションを構成する要素は、「公平感」、「達成感」、「連帯感」の3つしかないのであり、社員のモチベーションアップを考えている企業は、この3つに効く施策を打つ必要がある(もちろん、先ほど登場した「リーダーシップ」や「経営慣行」も、この3要素に影響を与える。例えば、明確で正当な評価基準に基づく信賞必罰が風土として染みついている企業であれば、社員の「公平感」が刺激される)。
ここで、「モチベーション」と「自己信頼」の構成要素を比較してみると、「連帯感」と「良好な人間関係」はぴったり重なると思う。「達成感」には、「過去の仕事の達成感」に加えて、「将来的に大きな仕事をやらせてもらえるかもしれない」という期待も含まれているので、この点では「未来への希望」と重なる部分がある(なお、先日の記事で述べたように、「未来への希望」と「自己への信頼」は部分的に重複している印象があるので、「達成感」と「自己への信頼」も重なる部分があると言えそうだ)。だが、「公平感」に関しては「自己信頼」と重なる要素がない。したがって、「自己信頼」と業績の間に相関関係が見られるかどうかは、個人的にはやや怪しいと推測している。


